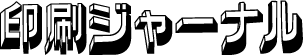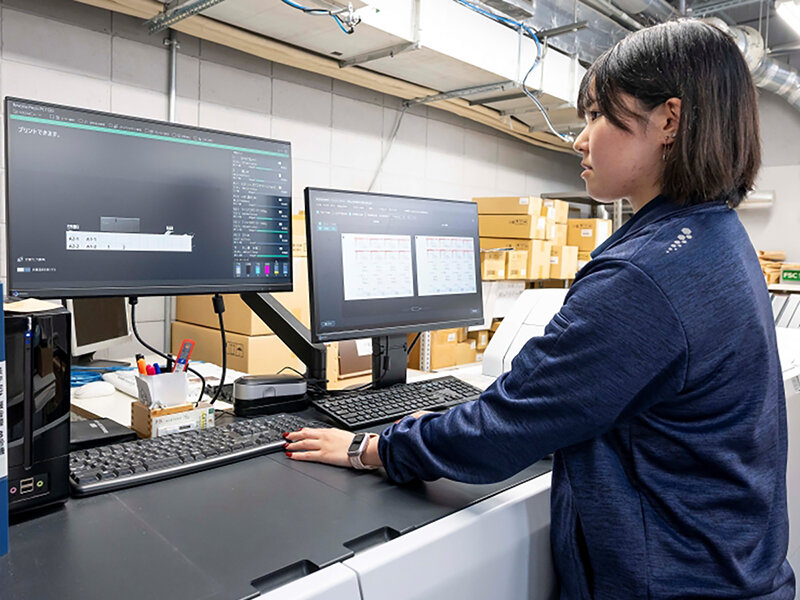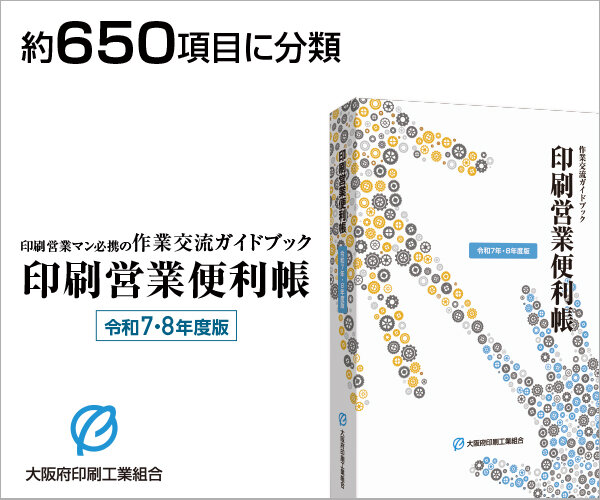プロカラーラボ、全国5つのラボにエコリカ直管形高演色LED設置
1,000本を演色AA蛍光灯から入換〜5年越しで出会った待望のLED
プロのための総合カラーラボである(株)プロカラーラボ(西宮本社ラボ/兵庫県西宮市石在町12-6)は創業以来、メーカー任せにしない現像処理や機械改良を重ね、「抜けのいいネガ」で業界に名を馳せてきた写真ラボである。人によって異なる色の見え方を揃えるため、最終チェックを一人の目に集約する厳格な検査文化も受け継いできた。そんな同社は昨年、全国5拠点のラボでエコリカの直管形高演色LEDを導入し、1,000本超を「演色AA(ダブルA)」の蛍光灯から入れ換えた。LED化は5年以上前から検討してきたが、肌色再現の違和感などから踏み切れずにいたという。西宮本社ラボ技術部の藤川欣也次長に話を聞いた。

抜けのいいネガに始まる独自の品質思想
同社が業界で存在感を高めていった原点は、フィルム時代に追求してきた「抜けのいいネガ」にある。当時、写真ラボの多くはメーカー指定の処理条件を忠実に守ることで品質の均一化を図っていた。しかし同社は、それではどこで現像しても同じ仕上がりになり、競争力にはならないと考えたという。
「メーカー系のラボはどこでやっても同じ仕上がりになる。でも、それでは面白くないし、選ばれる理由にならないと当社は考えた」
現像温度や補充量などの条件を一つひとつ見直し、従来よりも階調が素直につながるネガづくりを徹底。その結果生まれたのが、暗部が重くならず、プリント時の調整幅が広い「抜けのいいネガ」であった。営業写真の現場ではこのネガが高く評価され、評判が評判を呼ぶかたちで同社の名は一気に広がっていった。
さらに同社は、仕上がりの安定性を左右する引き伸ばし機にも踏み込んでいった。当時の機械はばらつきが大きく、1枚目は良くても2枚目で色が合わないことも珍しくなかった。
「1枚きれいに出すことはできても、同じ色を続けて出せない。それが一番困っていた」
冷却ファンの追加など独自の改良を重ね、最終的には自社で引き伸ばし機を大量に製作するまでに至った。人が機械に合わせるのではなく、理想の仕上がりに機械を近づける。その姿勢は、デジタル化が進んだ現在においても、同社のものづくりの根幹として息づいている。
人によって違う色の見え方を、どう揃えるか
色の仕事において避けて通れないのが、人による「見え方」の違いである。同じプリントを見ても、ある人は赤く感じ、別の人は黄色寄りに感じることもある。同社では、この個人差こそが品質を不安定にする最大の要因だと考えてきた。
「極端な話だと、私には赤に見えても、別の人には黄色に見えることがある。それくらい、人によって見え方は異なる」
そこで同社では、誰が作業しても同じ仕上がりにするため、最終検査を一人の目に集約する仕組みを構築した。
「3人で検査すれば、3通りの色が出てしまう。でも1人なら、その人の目が基準になる」
この基準となる目は、先代社長が長年担ってきた非常に厳しい検査だったというが、その厳しさの中で育った人材が、同社の品質を支えてきた。藤川氏も、その教育を受けてきた一人だ。
「怒られることも多かったが、その経験があったからこそ、今があると思っている」
現在では、そうした教育を受けたベテランは少なくなりつつあるが、考え方は変わらない。若手社員に対しても同じ基準で検査を行い、「プロカラーラボとしての品質」を揃え続けている。この「見え方を揃える」という思想は、後に照明を選ぶ際の判断基準にも、そのままつながっている。
三波長蛍光灯の普及が突きつけた写真館での見え方の変化
同社が照明の重要性を強く意識するようになったきっかけは、フィルム時代に経験した「三波長蛍光灯」の問題であった。長年、同社ではパナソニックの自然色タイプ、いわゆる演色AA(ダブルA)の蛍光灯を使用してきた。決して完璧な光源ではないものの、フィルム時代から使い慣れた光であり、色判断の基準としては安定していたという。
ところが、ある時期から市場に三波長タイプの蛍光灯が普及し始めた。赤を強調し、被写体を鮮やかに見せる特性を持つ光源で、一般家庭や写真館にも急速に広がっていった。
「今までと同じようにプリントしているのに、ある時期から突然、『赤い』というクレームが一気に増えた」
原因を突き止めていく中で分かったのが、写真館側の照明環境の変化であった。ラボと写真館で使用している蛍光灯の種類が異なれば、同じプリントでも見え方は大きく変わる。照明が変わることにより、色評価そのものが変化するということを初めて痛感した。
その対策として同社は、三波長タイプを判別できる場所を設けたり、蛍光灯を1本おきに混ぜたりするなど、現場でできる工夫を重ねてきた。営業写真の世界では、写真館の環境こそが「基準」になる。100件の写真館があれば、100通りの見え方がある。それぞれの写真館の見え方に対応するため、同社では写真館の担当は専任の技術社員がついて仕上がりの好みを把握するようにしております。藤川氏も入社以来、30数年以上にわたって担当している写真館もあるという。
照明が色評価を左右するという中、見えてきた選択肢がLEDであった。蛍光灯は、いずれ製造終了になることが分かっているため、将来的にLEDへ移行する流れは避けられない。同社でも、LED化の検討自体は5年以上前から続けていたという。
しかし、初期のLEDは同社の求める水準には到底届かなかった。特に問題となったのが、肌色の再現性である。「最初の頃のLEDは、色評価指数が80とか、ひどいものだと70台もあった。あれで見ると、顔が全部茶色く見える。これは使えないなと...」
その後、東芝やパナソニックなどの大手メーカーから、高演色タイプのLEDが登場。同社でもすぐに取り寄せて検証を行った。数値は悪くないが、実際にプリントを見ると、長年使ってきた自然色蛍光灯と比べ、肌色の出方にわずかな違和感が残ったという。
「悪くはないのだが、今までの蛍光灯に慣れた目で見ると、どうしても違う。これを現場に入れたら、仕上がりがバラつくと感じた」
美術館向けとして発売された高演色LEDを導入する計画も立ち上がったこともあった。色の影響を受けにくい製本や発送部門に試験的に設置し、様子を見ることにしたが、結果は芳しくなかったという。
照明を変えること自体が目的ではない。このため、同社は無理にLED化を進めることはせず、「本当に納得できるものが出るまで待つ」ことを選択した。そして、満を持して出会ったのが、昨年に導入したエコリカの直管形高演色LEDであった。
5年越しに巡り合った待望のLED。目の負担、省エネ効果も顕著に
同社がエコリカのLEDを見つけたのは、昨年2月に開催されたpage2025であった。東京拠点の社員がエコリカの高演色LEDを目にし、藤川氏に「これはいけますよ」と連絡してきたという。まずは東京の建物に数本を設置し、実際に判断できる環境を整えた上で、藤川氏が現地で確認することになった。
「見た瞬間に『これなら大丈夫』と思った」
決め手となったのは、長年使い続けてきた自然色蛍光灯と比べても、見え方の変化が極めて小さかった点だ。明るさはやや増したものの、色調そのものに大きな違和感はなく、現場が混乱しないと判断したという。
「急に見え方が変わると仕上がりにバラつきが出てしまう。ただ、エコリカのLEDだけは、これまで使っていた蛍光灯とほとんど変わらなかった。明るさは調整すればいいと判断した」

また、分光波長のバランスの良さも評価したポイントの1つだ。さらに、器具を替えずにランプのみ交換できる直管形であることも、全国5拠点・1,000本超という規模での導入を後押しした。LEDは1本あたりの単価が高く、すべてを入れ替えるとなるとコスト負担は大きい。その点、エコリカは現実的な選択肢であったという。製本工場には通常のLEDを採用するなど、用途に応じた使い分けも行い、昨年9月から11月にかけて順次切り替えを進めた。
導入後、最初の1週間ほどは光がシャープに感じられたものの、作業が混乱することはなかった。むしろ、フリッカーレスによる目の負担軽減や、照度低下の少なさといった効果を実感しているという。「ずっとモニターやプリントを見る仕事なので、目が楽になったのは大きいと感じている」
さらに、省エネ効果も顕著である。照明だけで電力使用量は約30%削減され、発熱量の低下により夏場の空調効率も向上した。さらに、紫外線量が大幅に減ったことで、目への負担も軽減されている。
ラボ業界を取り巻く環境は厳しさを増しているようだが、藤川氏はポジティブに捉える。
「写真を撮る人が減っている今だからこそ、業界を盛り上げていける存在でありたい。品質で支え続けるラボでありたいと思っている」